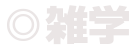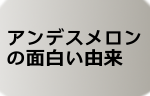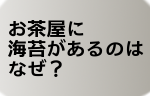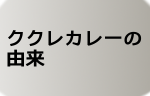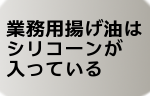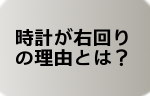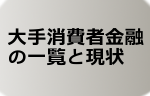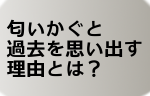恵方巻きの由来とは?
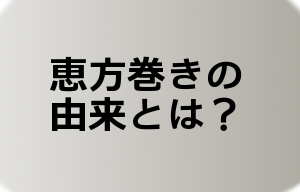
2月3日の節分の日には恵方巻を食べる。
知らぬ間に一般的になってしまっている不思議な行事です。
実は「恵方巻き」という名称は極めて最近に作られた名称というのは知っていましたか?
恵方巻きの由来

※引用元:恵方巻き(wikipedia)
恵方巻きの「恵方」は、
陰陽道でその年の干支によって定められた最も良いとされる方角のことです。
恵方にはその年の福徳を司る神「歳得神(としとくじん)」が存在すると言われています。
※歳得神とは?(wikipedia)
その恵方に向かって神に願いごとをしながら巻き寿司を食べることから、
「恵方巻」と呼ばれるようになりました。
が、この「恵方巻」という名称はセブンイレブンが名付けた商品名です。
当初は「丸かぶり寿司 恵方巻」として売られていました。
恵方巻きの本当の名前・由来は?

正しくは「丸かじり寿司」など、地域により名称が様々あります。
そして由来はよくわかっていません。
大阪発祥の可能性は高く、商売繁盛を願うもの?など様々な説があります。
一度は廃れた行事でしたが、大阪の商売根性で復活させ、
最後はセブンイレブンなど大手が頑張って、現在の普及率になったようです。
名称はいろいろあり、
「丸かぶり寿司」や「丸かじり寿司」、「節分の巻きずし」、「幸運巻きずし」とも呼ばれます。
ここまで統一されていないということは、そもそも決まった名称は無かったのでは?とも思います。
そうたいした文化でもなかったのでしょう。
巻き寿司を切らず一本丸ごと食べるのは、
「縁を切らない」という意味が込められており、
七福神にちなんで「かんぴょう」「きゅうり」「伊達巻」「うなぎ」など7種類の具材が入れられ、
「福を巻き込む」という願いも込められています。
しかし、これも文化としては無く、値段を高くするための商売根性か?という気もします。
そんなよくわからない恵方巻ですが、
恵方の神に願い事をするということは、良いことだと思います。
大きな巻き寿司を丸ごと食べる機会なんてそう無いので、
楽しんでおきましょう。
さらに詳しく知りたい人は「恵方巻(wikipedia)」をどうぞ。
--
以上、恵方巻きの由来とは?でした。
スポンサーリンク
--
現在、コメント投稿はできません。
--
トップページ→◎雑学
この記事の作成日:2015年01月29日
--
その他コンテンツ